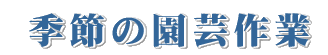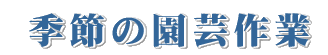病害虫の防除

トウガラシの煎汁を
小型のアオムシの防除に
|
暑さで弱った株は、病害虫もつきやすいもの。早めに見つけて、被害が大きくならないように対処しましょう。害虫は早めに見つけて、早期駆除。病気は発生しないように丈夫に育てるのが大切で、油粕などチッソ肥料のやりすぎは、軟弱に育つ原因になりますので避けましょう。
草や木も、繁りすぎたところは枝をすかしてやり、風通しよく育てれば、病害虫の発生も少なく、たとえ発生してもすぐにわかるので早めの対策が取れます。毛虫や青虫などの大型の虫は、早めに見つけて箸などでつまんでビニール袋にいれて処理すればよいでしょう。大量に発生したときや、ツバキやサザンカにチャドクガが出たときは、やはり農薬の散布が必要です。虫の体に掛かるようスミチオン乳剤を散布します。アブラムシは、牛乳を生のままスプレーで散布すれば退治できます。これは牛乳の脂肪分がアブラムシの体を被って窒息させたり、圧縮死させるものです。2、3日後に頭から、潅水して牛乳分を洗い流しましょう。ハダニにはコーヒーの飲み残しがききますし、ハーブ類(バジル、チャイブ、トウガラシ、ニンニクなど)の煮出し液もいろいろ効果があるようで、防虫のほか、うどんこ病の予防によいといわれます。
また、最近話題になっているのが木材を燃やしたときに出る煙の成分を集めた「木酢液」。草花の体質改善や病気の予防に効果があると、無農薬栽培を目指す菜園やハーブ作りの方に好評です。スプレー式のものも出ていますので使いやすいですね。草花類のうどんこ病にも効果があるようです。いずれにしろ、病虫害対策は、早め早め発生を見つけて対策をとるのが大切。こまめに庭に出かけましょう。
|
|