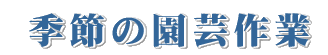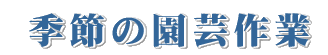買い物情報
 |
風に揺れると涼しげな
ヒコウキソウ |
 |
葉の白と果色の橙色が
鮮やかな“スノーサンゴ” |
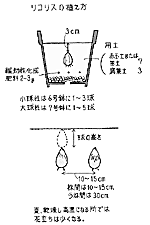 |
涼しげな鉢物のニューフェイス
蒸し暑い夏の時期は涼を運んでくれる鉢物がよいですね。近年は風で揺れるタイプのものや葉に白の斑入りや縞が入るものの人気が高まっているようです。ヒコウキソウやフウチソウなど風に揺れるタイプは水切れに注意しましょう。斑入りフユサンゴ“スノーサンゴ”やカラジウム・キャンディタムなど斑入りのものは元の種類より、直射日光に弱くなっているものが多いので、直射日光には注意が必要です。(*ここで取り上げた鉢物の管理方法はメールマガジン園芸ファン通信6月25日号に載っています。ご覧ください)。
長く咲き続ける真夏の花鉢物
夏の暑さに負けずに咲いてくれるアサガオ、ポーチュラカ、インパチエンス、ハイビスカス、サルスベリ、ザクロなど熱帯・亜熱帯地方原産の鉢物の出番です。下葉までちゃんと付いていて、根元がぐらつかない根がしっかりとしているものを選びましょう。
秋咲き球根
ヒガンバナやショウキランなどのリコリス類に、アマリリス・ベラドンナ(本アマリリス)など秋咲きの球根類がショップに出まわり始めます。球根とはいっても、完全には休眠せず、根が生きているタイプが多いですから、なるべく早めに入手して、早めに植えつけるのがポイントです。アマリリス・ベラドンナは7月一杯、リコリス類、ステルンベルギアは8月中には植えつけましょう。
夏の花インパチエンスとその仲間
 |
可愛らしい八重咲きの
アフリカホウセンカ |
 |
花と葉が楽しめる
ニューギニア インパチエンス |
夏のシャドーガーデンに人気のインパチエンス。花壇や鉢物と用途の広いアフリカホウセンカ(普通のインパチエンス)と、近年導入された鉢物用のニューギニアインパチエンスが代表です。この「インパチエンス」という名前はツリフネソウ科ツリフネソウ属の属名で、日本にも山野草として親しまれているツリフネソウやキツリフネがあり、インド原産のホウセンカもこの仲間です。
アフリカホウセンカ
原産地熱帯アフリカ。最近の品種は日向の花壇にも耐え、耐陰性も強い。花壇のほか吊鉢、ハンギングバスケットにもよい。八重咲きや葉に斑が入る品種もある。
ニューギニアインパチエンス
ニューギニア原産の種類から改良された大型種。花は大輪で、葉に黄や赤の中斑が入り、鉢物として人気が高い。強光線に弱いので注意。明るい半日陰程度がベスト。
<インパチエンス栽培のポイント>
- 耐陰性は強いが、完全な日陰では長持ちしない。
- 水切れさせないように注意。過湿もよくない。
- 追肥をこまめに与えるが、チッソ過多にならないようにする。
- 株が茂りすぎると蒸れやすいので、適度に枝抜きをする。
- 枝が間延びしたら、切り戻しをして再生させるとよい。
- 冬は保護すれば、多年草として扱える。
- 繁殖は実生(アフリカホウセンカ)か、挿し芽。
入手した花鉢物の管理
化粧鉢で仕立てられた花鉢物は株に比べ、鉢が小さいものがほとんどです。これは、やや小さめの鉢で仕立てた方が見栄えがよく、輸送も楽なためです。しかしそのまま育てていると、根詰まりで水切れしやすく、花が咲き続ける期間も短くなりがちです。
ですから、鉢が小さめに感じられるものは、すぐに鉢替えしましょう。鉢からすっぽりと抜き、一回り大きい鉢に移すわけです。このとき使う土は、今まで植えられている土と同じ感じの土を使うのがポイント。根鉢も根を切らない程度にほぐし、深植えにならないように注意して植え付けます。そして花がらをこまめに摘み、追肥を月1回くらい施すようにすれば、夏一杯、種類によっては秋まで花を咲かせ続けてくれるはずです。
夏の病害虫の防除
梅雨時の高温多湿や真夏の猛暑は、人間と同様、多くの植物にとってつらいもの。多湿や暑さで弱った株は、病害虫がつきやすいので注意しましょう。
<病虫害の被害を大きくしない栽培ポイント>
株間をとり、適度な枝抜きで通風を図る
草や木も、繁りすぎたところは適度に枝をすかして風通しを図り、丈夫に育てること。株間も枝と枝が交差しないようにたっぷりとりましょう。そうすれば、病害虫の発生も少なく、発生しても見つけやすいので早めの対策が取れます。
肥料過多を避ける
肥料過多は病気が出やすくなる原因の一つ。特に油粕などチッソ肥料をやりすぎると、株が軟弱になり病気が出やすくなります。
<病害虫防除の方法>
早期発見早期駆除
早めに発見して、被害が大きくならないように対処することが大切。ケムシなどは孵化したてなら一箇所に集まっていますからに退治しやすく、病気も初期ならば、被害葉の摘み取りだけでも、蔓延をそうとう防ぐことができます。
自然農薬の利用
アブラムシには牛乳を生のまま霧吹きでスプレーします。虫の体に牛乳が直接かけるのがポイント。ただ、1回で全部を駆除することはできませんから、3、4日おきに2、3回散布しましょう。相当に数を減らせるはずです。 また、コーヒーの飲み残しはハダニに、ハーブ類(バジル、チャイブ、トウガラシ、ニンニクなど)の煮出し液は防虫(ニンニクの煎じ汁は青虫類にも効くとのこと)、うどんこ病の予防などにいろいろ役に立ちます。試してみてください。
人気のラベンダー 種類と育て方
そろそろ富良野などでラベンダーの名所から花便りが届きはじめます。甘い香りと鮮やかな花で、ハーブの中でも人気の高いラベンダー、いくつかの系統があるのをご存知ですか。
<ラベンダーの系統と特徴>
 |
暖地向きの
フレンチラベンダー |
 |
四季咲きがあるが耐寒性の
やや弱いレースラベンダー |
- コモンラベンダー(イングリッシュラベンダー)系
- 普通にラベンダーというとこの種類。香りは強いのですが、夏の暑さに弱く、関東以南の暖地では作りにくい。耐寒性は強い。
- ラバンディン系
- コモンラベンダーとスパイクラベンダーの交配で生まれた種類。耐寒性、耐暑性共に強く、作りやすい。香りも強い。
- フレンチラベンダー系
- 早春に販売されるラベンダーはこの種類。花穂の先端の包が大きく目立つ。耐暑性は強いが寒さには弱い。暖地向き。
- フリンジラベンダー系
- 秋から春に咲くラベンダー。耐暑性は強いが寒さに弱い。香りはカンファー系(樟脳の香り)。暖地向き。
- スパイクラベンダー系
- 花茎が長く、花が飛び飛びに咲く。耐暑性、耐寒性あり。香りはカンファー系。
- そのほかの種類
- 以上の種類のほか、レースラベンダー(ファーンラベンダー)などの種類が導入されています。園芸品種は多くなく、あまり香りが強くないものが多いようです。
<ラベンダーの鉢栽培>
- 適する地域
系統によって耐暑性、耐寒性が違いますので、暖地では耐暑性の強い、ラバンディン系、フレンチラベンダー系を選ぶようにしましょう。寒冷地ならばコモンラベンダー系が育てられます。
- 土と置き場所
植える用土は水はけのよい砂がちの土がよく、普通の庭土や黒土を使う場合はピートモスか腐葉土に川砂の類を2〜3割混ぜ込んでおきます。土の酸性改良ために、苦土石灰を6号鉢当たり1掴みほど加えます。 置き場所は日当たりと風通しがよい場所がよく、夏は西日が当たらない涼しいところに移します。
- 肥料と水やり
肥料はほとんどいりません。特にチッソ肥料(油粕など)の単用は禁物です。年に1回(春先)、有機配合肥料を少量施す程度で十分でしょう。石灰を加えていない場合は酸度の改良ために熔成燐肥を指先で軽く一掴みずつ3か所ほどに施すのも効果的です。肥料ではありませんが、夏前と冬の前に、根の保護のため根元に腐葉土を軽く敷いておくとよいようです。
水やりは、過湿を嫌いますので控え目に、土の表面が乾いてきたらたっぷりと与えるようにします。菜種梅雨、梅雨、秋の長雨には当てないようにします。
- 剪定
ラベンダーは自然のままに放任しておくと、蒸れて枯れてしまうことがあります。2、3年に1回は刈り込んでやりましょう。時期は開花後2週間ぐらいで、花茎の下、1、2枚葉をつけた辺りで刈り取り、合わせて株元の新枝も地面から10cmくらいまで整理し、株中、株元に風が入るようにします。また、高さの調節をしたい場合は、早春により深く切るようにします。
- 植え替え
鉢中に根が回ってきたら植え替えます。目安は3〜4年に1回でしょう。時期は秋(10月)か春(3月)です。
以上、ラベンダーの鉢栽培について説明しましたが、ラベンダーは鉢やプランターで長年育てるのは困難です。なるべく庭植えをお勧めします。基本的な栽培方法は同じです。
季節の園芸作業6月号に、お花見情報(アジサイの名所)と、梅雨時の挿し木の仕方、人気のワイルドストロベリーの育て方が載っています。ご覧ください。
|